「七福神」は”7つの福の神”と書くので、福をもたらしてくれる神様だと誰でも想像できますが、7柱の名前やご利益、見分け方などをきちんと説明できる方は少ないと思います。
そこで今回は、「七福神」の名前・ご利益・見分け方などを徹底解説します。
 がお
がお「七福神」って誰でも知ってるけど詳細を説明できる?
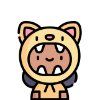
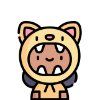
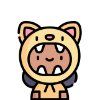
有名どころの名前しかわからないや。
「七福神」とは?


「七福神」とは福をもたらすとして日本で信仰されている「七柱」の総称で、セットで数えられるようになったのは、室町時代末頃の近畿地方が始まりとされています。
「七福神」に数えられる「七柱」はそれぞれ起源が異なり、元々はヒンドゥー教・仏教・道教・神道など、別々に信仰されていた神様で、今では縁起物として全国の神社やお寺で祀られています。
- ヒンドゥー教:インドの民族宗教
- 仏教:インドの釈迦を開祖とする宗教
- 道教:中国の宗教
- 神道:日本の宗教
江戸時代には現在の恵比寿・大黒天・毘沙門天・弁財天・布袋・寿老人・福禄寿にほぼ定着したものの、その後もメンバーを入れ替えた別パターンの「七福神」が生み出されることもありましたが、定着しませんでした。
「七福神」の特徴
「七福神」のザックリとした特徴は以下です。
| 持ち物 | 服装・特徴 | 主なご利益 | |
|---|---|---|---|
| 恵比寿 | ・釣り竿 ・鯛 | ・狩衣 ・指貫 ・烏帽子 | ・商売繁盛 ・五穀豊穣 ・大漁守護 ・除災招福 |
| 大黒天 | ・打ち出の小槌 ・袋 | ・頭巾 ・米俵 | ・商売繁盛 ・五穀豊穣 ・出世開運 ・子孫繁栄 |
| 毘沙門天 | ・宝棒 ・宝塔 | ・甲冑 | ・武道成就 ・降魔厄除 ・家内安全 ・夫婦和合 |
| 弁財天 | ・琵琶 | ・羽衣 | ・恋愛成就 ・学徳成就 ・諸芸上達 ・福徳施与 |
| 布袋 | ・杖 ・袋 | ・太鼓腹 | ・商売繁盛 ・金運招福 ・夫婦円満 ・家運隆盛 |
| 寿老人 | ・巻物付きの杖 ・桃 | ・牡鹿 | ・幸福長寿 ・家庭円満 ・延命長寿 ・福徳智慧 |
| 福禄寿 | ・杖 ・巻物 | ・鶴 | ・財運招福 ・延命長寿 ・招徳人望 ・子孫繁栄 |
| 持ち物 | 服装・特徴 | 主なご利益 | |
|---|---|---|---|
| 恵比寿 | ・釣り竿 ・鯛 | ・狩衣 ・指貫 ・烏帽子 | ・商売繁盛 ・五穀豊穣 ・大漁守護 ・除災招福 |
| 大黒天 | ・打ち出の小槌 ・袋 | ・頭巾 ・米俵 | ・商売繁盛 ・五穀豊穣 ・出世開運 ・子孫繁栄 |
| 毘沙門天 | ・宝棒 ・宝塔 | ・甲冑 | ・武道成就 ・降魔厄除 ・家内安全 ・夫婦和合 |
| 弁財天 | ・琵琶 | ・羽衣 | ・恋愛成就 ・学徳成就 ・諸芸上達 ・福徳施与 |
| 布袋 | ・杖 ・袋 | ・太鼓腹 | ・商売繁盛 ・金運招福 ・夫婦円満 ・家運隆盛 |
| 寿老人 | ・巻物付きの杖 ・桃 | ・牡鹿 | ・幸福長寿 ・家庭円満 ・延命長寿 ・福徳智慧 |
| 福禄寿 | ・杖 ・巻物 | ・鶴 | ・財運招福 ・延命長寿 ・招徳人望 ・子孫繁栄 |
恵比寿さま


| 恵比寿 | |
|---|---|
| 出自 | 日本の神様 |
| 起源 | イザナギとイザナミとの間に生まれた最初の子ども |
| 持ち物 | ・右手に釣り竿 ・左手に鯛 |
| 特徴 | ・狩衣(かりぎぬ) ※狩りのときの服 ・指貫(さしぬき) ※袴の一種 ・風折烏帽子(かざおりえぼし) ※頂が風に吹き折られた形の帽子 |
| ご利益 | ・商売繁盛 ・五穀豊穣 ・大漁守護 ・除災招福 |
| 恵比寿 | |
|---|---|
| 出自 | 日本の神様 |
| 起源 | イザナギとイザナミとの間に生まれた最初の子ども |
| 持ち物 | ・右手に釣り竿 ・左手に鯛 |
| 特徴 | ・狩衣(かりぎぬ) ※狩りのときの服 ・指貫(さしぬき) ※袴の一種 ・風折烏帽子(かざおりえぼし) ※頂が風に吹き折られた形の帽子 |
| ご利益 | ・商売繁盛 ・五穀豊穣 ・大漁守護 ・除災招福 |
「恵比寿」は釣り竿と鯛を持ち、狩衣・指貫・風折烏帽子を身に着けているのが特徴で、商売繁盛・五穀豊穣・大漁守護・除災招福などのご利益があります。
起源は日本神話に登場する伊邪那岐命(イザナギ)と伊邪那美命(イザナミ)の間に生まれた最初の子ども「蛭子(ヒルコ)」、もしくは大国主神(オオクニヌシノカミ)の息子である「事代主神(コトシロヌシノカミ)」などを祀ったものとされています。
古くは「大漁追福」の漁業の神でしたが、時代と共に福の神として「商売繁盛」や「五穀豊穣」をもたらす神となった唯一日本由来の神です。
大黒天さま


| 大黒天 | |
|---|---|
| 出自 | インドの神様 |
| 起源 | ヒンドゥー教のシヴァ神の化身マハーカーラ |
| 持ち物 | ・打ち出の小槌 ・袋 |
| 特徴 | 頭巾を被り米俵に乗っている |
| ご利益 | ・商売繁盛 ・五穀豊穣 ・出世開運 ・子孫繁栄 |
| 大黒天 | |
|---|---|
| 出自 | インドの神様 |
| 起源 | ヒンドゥー教のシヴァ神の化身マハーカーラ |
| 持ち物 | ・打ち出の小槌 ・袋 |
| 特徴 | 頭巾を被り米俵に乗っている |
| ご利益 | ・商売繁盛 ・五穀豊穣 ・出世開運 ・子孫繁栄 |
「大黒天」は打ち出の小槌と袋を持ち、米俵に乗っているのが特徴で、商売繁盛・五穀豊穣・出世開運・子孫繁栄などのご利益があります。
起源はヒンドゥー教のシヴァ神の化身であるマハーカーラで、”マハー”は「大(偉大)」、”カーラ”は「黒(暗黒)」を意味するので大黒天と名付けられ、元々は軍神・戦闘神・富貴爵祿(財福)の神とされていましたが、日本には”財福の神”の部分が強調されて伝えられました。
また日本神話に登場する神「大国主神(オオクニヌシノカミ)」の「大国」を”ダイコク”とも読めることや、両者とも豊饒に関わる神と信じられていたことなどから同一視されるようになり、後に習合されています。
毘沙門天さま
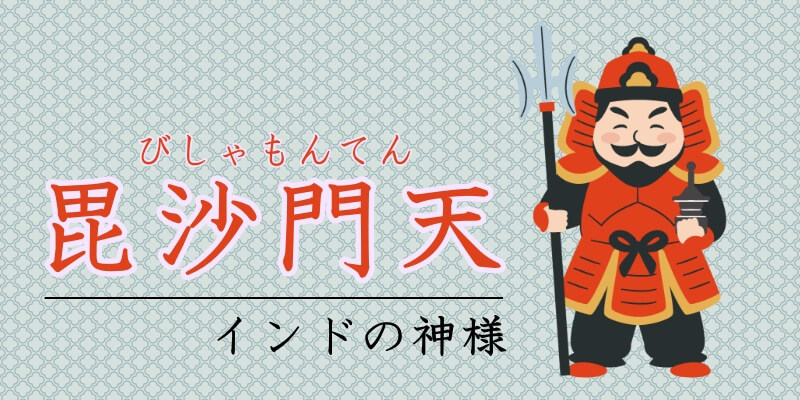
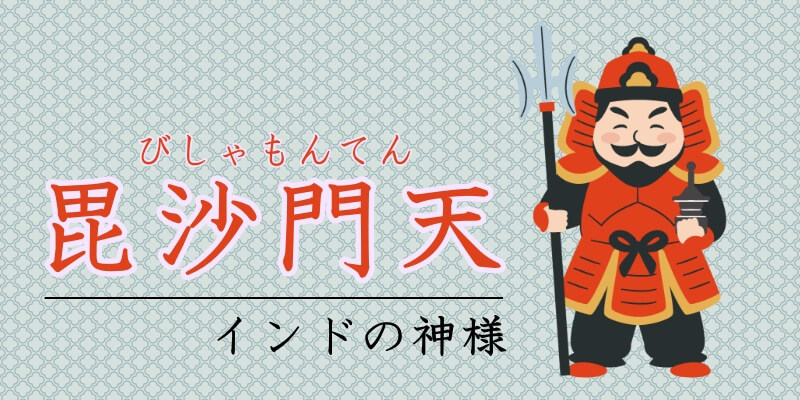
| 毘沙門天 | |
|---|---|
| 出自 | インドの神様 |
| 起源 | ヒンドゥー教のクベーラ神 |
| 持ち物 | ・宝棒 ・宝塔 |
| 特徴 | 甲冑を身に着けている |
| ご利益 | ・武道成就 ・降魔厄除 ・家内安全 ・夫婦和合 |
| 毘沙門天 | |
|---|---|
| 出自 | インドの神様 |
| 起源 | ヒンドゥー教のクベーラ神 |
| 持ち物 | ・宝棒 ・宝塔 |
| 特徴 | 甲冑を身に着けている |
| ご利益 | ・武道成就 ・降魔厄除 ・家内安全 ・夫婦和合 |
「毘沙門天」は宝棒と宝塔を持ち甲冑を身に着けているのが特徴で、武道成就・降魔厄除・家内安全・夫婦和合などのご利益があります。
インドでは財宝神とされ戦闘的なイメージはありませんでしたが、中央アジアを経て中国に伝わる過程で武神や守護神とされるようになりました。
毘沙門という名前はインド神話のヴァイシュラヴァナを中国で音写したもので「よく聞く所の物」という意味にも解釈できることから「多聞天(たもんてん)」とも呼ばれます。
仏教の世界観の中で中心にそびえる聖なる山である「須弥山(しゅみせん)」の中腹の四方を守護している四天王のうち、北方を守護しているのが多聞天です。
弁財天さま


| 弁財天 | |
|---|---|
| 出自 | インドの神様 |
| 起源 | ヒンドゥー教のサラスヴァティー神 |
| 持ち物 | 琵琶 |
| 特徴 | 羽衣を身に着けている |
| ご利益 | ・恋愛成就 ・学徳成就 ・諸芸上達 ・福徳施与 |
| 弁財天 | |
|---|---|
| 出自 | インドの神様 |
| 起源 | ヒンドゥー教のサラスヴァティー神 |
| 持ち物 | 琵琶 |
| 特徴 | 羽衣を身に着けている |
| ご利益 | ・恋愛成就 ・学徳成就 ・諸芸上達 ・福徳施与 |
「弁財天」は琵琶を持ち羽衣を身に着けているのが特徴で、恋愛成就・学徳成就・諸芸上達・福徳施与などのご利益があります。
起源はヒンドゥー教の女神であるサラスヴァティー神で、元々は水の女神でしたが、次第に芸術や学問などを司る女神と見なされるようになりました。
また元々の表記は「弁才天」でしたが、日本では財宝神としての側面に信仰が集まったため、「弁財天」と表記されることが多いです。
日本では神仏習合により神道にも取り込まれインドや中国で伝えられるものとは微妙に異なる性質を持ち、日本神話に登場する市杵嶋姫命(イシキシマヒメ)と同一視されることが多いです。
布袋さま


| 布袋 | |
|---|---|
| 出自 | 中国の神様 |
| 起源 | 実在したとされる伝説的な仏僧 |
| 持ち物 | ・杖 ・袋 |
| 特徴 | 太鼓腹 |
| ご利益 | ・商売繁盛 ・金運招福 ・夫婦円満 ・家運隆盛 |
| 布袋 | |
|---|---|
| 出自 | 中国の神様 |
| 起源 | 実在したとされる伝説的な仏僧 |
| 持ち物 | ・杖 ・袋 |
| 特徴 | 太鼓腹 |
| ご利益 | ・商売繁盛 ・金運招福 ・夫婦円満 ・家運隆盛 |
「布袋」は杖と袋を持ち太鼓腹が特徴で、商売繁盛・金運招福・夫婦円満・家運隆盛などのご利益があります。
「七福神」の中で唯一実在したとされる伝説的な仏僧で、本来の名は「契此(かいし)」といいますが、常に袋を背負っていたことから布袋という俗称がつけられました。
またお寺には住まず、施しを受けながらあちこちを泊まり歩いたといい、素直な気持ちの持ち主で人々を満ち足りた気持ちにさせたり、吉凶を言い当てたりと不思議な力を持っていた逸話があります。
日本では福の神として信仰を集め、肥満体は広い度量や円満な人格、富貴繁栄を司ると考えられ、所持している袋は不満や嫌なことを溜め込む「堪忍袋」と見なされるようになりました。
寿老人さま


| 寿老人 | |
|---|---|
| 出自 | 中国の神様 |
| 起源 | 南極老人星の化身 |
| 持ち物 | ・巻物付きの杖 ・桃 |
| 特徴 | 牡鹿を従えている |
| ご利益 | ・幸福長寿 ・家庭円満 ・延命長寿 ・福徳智慧 |
| 寿老人 | |
|---|---|
| 出自 | 中国の神様 |
| 起源 | 南極老人星の化身 |
| 持ち物 | ・巻物付きの杖 ・桃 |
| 特徴 | 牡鹿を従えている |
| ご利益 | ・幸福長寿 ・家庭円満 ・延命長寿 ・福徳智慧 |
「寿老人」は巻物付きの杖と桃を持ち、牡鹿を従えているのが特徴で、幸福長寿・家庭円満・延命長寿・福徳智慧などのご利益があります。
道教の神で中国の伝説上の人物、南極老人星(カノープス)の化身とされており、寿老人と福禄寿は胴体異名の神とされることもあります。
手に持っている桃は長寿のシンボルで、従えている牡鹿は長寿と自然との調和のシンボルです。
福禄寿さま


| 福禄寿 | |
|---|---|
| 出自 | 中国の神様 |
| 起源 | 寿老人と同体異名の神とされる |
| 持ち物 | ・杖 ・巻物 |
| 特徴 | 鶴を従えている |
| ご利益 | ・財運招福 ・延命長寿 ・招徳人望 ・子孫繁栄 |
| 福禄寿 | |
|---|---|
| 出自 | 中国の神様 |
| 起源 | 寿老人と同体異名の神とされる |
| 持ち物 | ・杖 ・巻物 |
| 特徴 | 鶴を従えている |
| ご利益 | ・財運招福 ・延命長寿 ・招徳人望 ・子孫繁栄 |
「福禄寿」は杖と巻物を持ち、鶴を従えているのが特徴で、財運招福・延命長寿・招徳人望・子孫繁栄などのご利益があります。
元々は福星・禄星・寿星の三星をそれぞれ神格化した三位一体の神でしたが、日本では3人ではなく1人の神とする認識が流布したとされます。
「七福神めぐり」でご利益を得る
「七福神めぐり」とは、恵比寿・大黒天・毘沙門天・弁財天・布袋・寿老人・福禄寿を祀っている神社やお寺を順番に巡り、それぞれの神様のご利益を受けるというものです。
「七福神めぐり」のコースは都道府県ごとに複数存在しており、ご自身が巡りやすいコースを選ぶと良いです。
まとめ
福の神として知られる「七福神」は、いずれも特徴的な服装や持ち物を持っているため、それらを目印にすると比較的覚えやすいです。
機会があれば、ぜひ楽しみながらマイペースで「七福神めぐり」をやってみてください。



人混みの多い観光地などは行きづらいから、ゆっくりと「七福神めぐり」は良いかもしれないね。
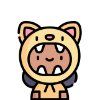
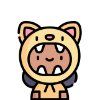
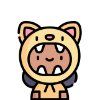
「七福神」のご利益得られたら何でも解決できちゃいそう!



コメント